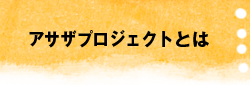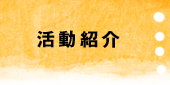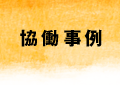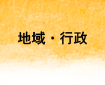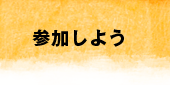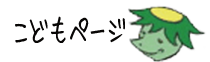2022年10月23日日曜日~25日火曜日
「谷津田で、稲刈・オダ掛け・脱穀アルバイトを募集しています。」



谷津田 谷津田 アサザの古民家
霞ケ浦の水源地 谷津田は湧き水の田んぼなので、機械が入らないため、手刈り、天日干しという昔ながらのやり方で美味しいお米を作っています。力を合わせて、稲刈りアルバイトで、良い汗を流しませんか?1年中水の湧いている泥の深い田んぼ。昔からお米が作られてきたところです。
〇期間 2022年10月23日日曜日〜10月25日火曜日
※3日間の内で、ご都合に合わせて 1日~ 大丈夫です。
〇募集定員: 1~2名(各日)
〇作業時間 8:00~17:00(休憩時間1時間)時給900円
※遠方の方は、アサザ基金の古民家に宿泊出来ます。(一泊素泊まり500円)
ウッドボイラーのお風呂、竹を燃料にした釜戸で自炊が可能です。
〇お申込み、お問い合わせ先
NPO法人アサザ基金(担当 きみしま)
mail: asaza@www.asaza.jp